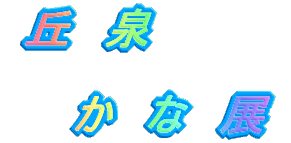 2
2小倉百人一首
名称
「小倉百人一首」とは、百人の作者の歌を各一首ずつ集めた歌集をいうが、この「小倉百人一首」はその代表的なものである。「小倉」とは小倉山のことで、今の京都市右京区嵯峨にあり、そこの藤原定家(ふじわらさだいえ又はていかともいう)の山荘「時雨亭」があった。その章子(今の襖)に和歌を書きつけた色紙がはられていたので、これを「小倉山荘色紙和歌」「嵯峨山荘色紙和歌」とも呼ぶが、「小倉百人一首」という名称が一般的である。
成立
定家の日記「明月記」では、嘉禎元(1235)年5月27日をその原型「百人秀歌」の成った日としている。選者については、藤原定家を中心とした宇都宮入道頼綱や飯尾宗祇らとする説があるが、定家選の「百人秀歌」を基にして、後の人が修補の手を入れているとする説が最も有力である。
内容
歌はすべて勅撰和歌集から選ばれている。定家は八代集から気に入った1800首を抄出し、「二四代集」としていたが、92首まではこれから選らばれている。また、部立てから見ると、恋が半数近くを占め、四季の中では秋が最も多い。これは、定家が余情、妖麗を重んじたことの反映とも考えられよう。哀傷、神祇、釈教が選ばれていないのも、そのような理念的なものには、襖に書く歌として適当なものがないからであろう。
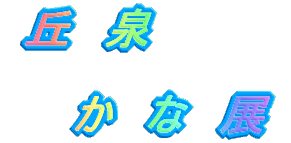 2
2
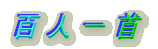
▲ スタートボタンを押してください。
自然に画像が変化します。
■ 中止するときはストップボタンを
おしてください。